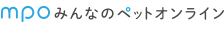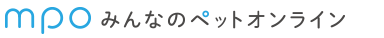犬の多頭飼いで喧嘩になる原因

縄張り意識
犬は自分が安全・安心して暮らせる場所をテリトリーとし、縄張りのように守ろうとする性質をもっています。
新しく犬やほかの動物を迎えると、先住犬は「自分のテリトリーを脅かす存在」と認識し、縄張り意識が強くなる傾向があります。
とくに、ソファの一角や自分専用のペットベッド、サークルなどお気に入りの場所にほかの犬が入ると、それがきっかけで大きなけんかに発展することもあります。
新しく犬やほかの動物を迎えると、先住犬は「自分のテリトリーを脅かす存在」と認識し、縄張り意識が強くなる傾向があります。
とくに、ソファの一角や自分専用のペットベッド、サークルなどお気に入りの場所にほかの犬が入ると、それがきっかけで大きなけんかに発展することもあります。
奪い合い
テリトリーだけでなく、食べ物やおもちゃなど物に対する所有欲も、けんかになる原因の一つです。
「お気に入りのもの、自分のものを奪われる」という危機感は、時には物だけでなく、飼い主の注意や愛情が対象になることもあります。
また、先住犬が新入りの犬を威嚇や攻撃するだけでなく、新入りの犬や若い犬のほうが威嚇する場合もあります。
「お気に入りのもの、自分のものを奪われる」という危機感は、時には物だけでなく、飼い主の注意や愛情が対象になることもあります。
また、先住犬が新入りの犬を威嚇や攻撃するだけでなく、新入りの犬や若い犬のほうが威嚇する場合もあります。
ストレス、体調不良
犬は環境の変化や運動不足などによってストレスがたまり、ストレスがたまると「我慢の限界」が近づいてイライラしやすくなり、ほかの犬や動物の行動に過敏に反応することがあります。
体に痛みや不快感があるときや、メスが妊娠しているときには防衛的になりやすく、ほかの犬が近づくだけで威嚇する場合もあります。
体に痛みや不快感があるときや、メスが妊娠しているときには防衛的になりやすく、ほかの犬が近づくだけで威嚇する場合もあります。
発情期
発情期のメスがいると、周囲のオス犬は行動が変化し、攻撃的になる可能性が高まります。
とくに未去勢のオスは、発情期中のメスに対する執着心が強くなり、近くのオス犬をけん制し、強く威嚇するなど、一触即発の行動に出たり、けんかになったりすることがあります。
また、発情しているメス自身も相手を選ぶため、意に沿わないオスに対して威嚇や攻撃をする場合があります。
とくに未去勢のオスは、発情期中のメスに対する執着心が強くなり、近くのオス犬をけん制し、強く威嚇するなど、一触即発の行動に出たり、けんかになったりすることがあります。
また、発情しているメス自身も相手を選ぶため、意に沿わないオスに対して威嚇や攻撃をする場合があります。
喧嘩とじゃれ合いの違いや見分け方

犬同士が本気でけんかをすると、取り返しのつかない事態になることも……。じゃれ合いではなく本気のけんかをはじめそうになったら、飼い主は止めなくてはいけません。
犬同士の仲が悪い場合、以下のような様子が見られます。
犬同士の仲が悪い場合、以下のような様子が見られます。
歯をむき出している
目を吊り上げ、鋭い視線で相手を見据えながら、鼻にしわを寄せて歯をむき出しにします。
顔は正面を向いているとは限らず、横顔を見せながら歯をむき出していることもあり、正面向きでも横向きでも、体は硬直し全身に力が入っています。
このような状態であれば、ちょっとしたきっかけで突進し、けんかに発展する危険性が高くなります。
一方、遊びでじゃれたがっている場合、鼻にしわを寄せて歯をむき出すことはほとんどありません。
表情も柔らかく、手足を動かして相手を挑発しながら楽しんでいる様子がうかがえます。
顔は正面を向いているとは限らず、横顔を見せながら歯をむき出していることもあり、正面向きでも横向きでも、体は硬直し全身に力が入っています。
このような状態であれば、ちょっとしたきっかけで突進し、けんかに発展する危険性が高くなります。
一方、遊びでじゃれたがっている場合、鼻にしわを寄せて歯をむき出すことはほとんどありません。
表情も柔らかく、手足を動かして相手を挑発しながら楽しんでいる様子がうかがえます。
唸り声をあげている
不快感や強いストレスを感じると唸り声をあげることがあります。
歯をむき出す、背筋からしっぽの毛を逆立てるなどの威嚇のしぐさに加えて、低く長い唸り声を続けているときは要注意。
「これ以上、自分を不快にさせるな」という警告として、唸り声をあげながら相手の動きを観察し、けん制しています。
同時に、いつでも飛びかかれるように体を硬直させているため、けんかに発展する可能性が高い状態です。
歯をむき出す、背筋からしっぽの毛を逆立てるなどの威嚇のしぐさに加えて、低く長い唸り声を続けているときは要注意。
「これ以上、自分を不快にさせるな」という警告として、唸り声をあげながら相手の動きを観察し、けん制しています。
同時に、いつでも飛びかかれるように体を硬直させているため、けんかに発展する可能性が高い状態です。
毛が逆立っている
犬は緊張・警戒しているとき、心理的ストレスを感じているときに、防衛本能の一部として毛を逆立てることがあります。
首筋から背骨に沿って毛が逆立ち、しっぽも立ち上がっていることが多いです。
そのまま姿勢を低くしたり、前傾姿勢になっていたりする場合は、いきなり飛びかかることがあるため注意が必要です。
首筋から背骨に沿って毛が逆立ち、しっぽも立ち上がっていることが多いです。
そのまま姿勢を低くしたり、前傾姿勢になっていたりする場合は、いきなり飛びかかることがあるため注意が必要です。
しっぽが下がっている
唸ったり歯をむき出したりする強気な状態だけでなく、不安や恐怖が強いときにも、けんかに発展することがあります。
こうしたケースではしっぽが下がっており、弱々しく振っていたり、足の間に巻き込んでいたりする様子も見られます。さらに体全体が硬直したり、震えていたりする場合は、極度のストレス下にあることが多く、限界に達すると反撃に転ずることも。
ただし、しっぽを左右に大きく振って表情もリラックスしている場合は、遊びたい、じゃれたいというアピールになります。
こうしたケースではしっぽが下がっており、弱々しく振っていたり、足の間に巻き込んでいたりする様子も見られます。さらに体全体が硬直したり、震えていたりする場合は、極度のストレス下にあることが多く、限界に達すると反撃に転ずることも。
ただし、しっぽを左右に大きく振って表情もリラックスしている場合は、遊びたい、じゃれたいというアピールになります。
多頭飼いの喧嘩の予防

飼い主は平等に接するよう心がける
複数頭の犬を飼うとき、1頭だけを優先すると、ほかの犬は嫉妬心から不安定になってしまいます。
犬同士の気持ちのすれ違いや不満を軽減し、けんかを予防するためには、どの犬にも平等に接することが大切です。
とくに、それまで単独飼育だったところに新しい犬を迎える場合は、先住犬の気持ちを十分に考慮することが重要です。
どの犬も飼い主から同じように愛されていると感じるようになると、犬同士の関係にもよい影響を与えます。
犬同士の気持ちのすれ違いや不満を軽減し、けんかを予防するためには、どの犬にも平等に接することが大切です。
とくに、それまで単独飼育だったところに新しい犬を迎える場合は、先住犬の気持ちを十分に考慮することが重要です。
どの犬も飼い主から同じように愛されていると感じるようになると、犬同士の関係にもよい影響を与えます。
ストレスに注意する
ストレスが強く精神的な負荷が大きい状況では、普段はできる「我慢」ができなくなり、けんかに発展しやすくなります。ストレスの原因は環境の変化、生活リズムの乱れ、ほかの犬との関係性、運動不足や睡眠不足など、さまざまです。
多頭飼育ではどの犬も満足できるように、十分な散歩や遊びの時間を確保し、安心して過ごせるスペースを用意しましょう。
また、体の痛みや体調不良がストレスの原因となることもあるため、定期的な健康チェックをおこなうことも大切です。
関連する記事
多頭飼育ではどの犬も満足できるように、十分な散歩や遊びの時間を確保し、安心して過ごせるスペースを用意しましょう。
また、体の痛みや体調不良がストレスの原因となることもあるため、定期的な健康チェックをおこなうことも大切です。
去勢・避妊手術をする
避妊や去勢の手術をすることで、攻撃的な行動が抑えられる可能性が高まります。
メスは、発情期特有のホルモン変化によるイライラ、周囲のオスを刺激する時期がなくなります。
また、オスはメスのホルモンによる刺激に影響を受けにくくなり、メスをめぐるほかのオスとの争いが減少します。
オス・メスともに、ほかの犬に対してリラックスしやすく、犬同士の関係が穏やかになります。
関連する記事
メスは、発情期特有のホルモン変化によるイライラ、周囲のオスを刺激する時期がなくなります。
また、オスはメスのホルモンによる刺激に影響を受けにくくなり、メスをめぐるほかのオスとの争いが減少します。
オス・メスともに、ほかの犬に対してリラックスしやすく、犬同士の関係が穏やかになります。
多頭飼いの喧嘩の対処法

飼い主が止めなくてもよいケースもある
新しい犬を迎えた直後は、関係性を築くプロセスとして、じゃれ合いから軽い衝突が起きることがあります。この場合、飼い主は必ずしも介入する必要はなく、介入の仕方によっては、かえって犬同士の関係が難しくなることもあります。
飼い主は冷静に状況を見守り、ボディランゲージやそれぞれの反応を継続的に観察しながら判断し、必要最低限の介入をすることが重要です。
飼い主が止めなくてもよいサインの具体的な例は以下の通りです。
飼い主は冷静に状況を見守り、ボディランゲージやそれぞれの反応を継続的に観察しながら判断し、必要最低限の介入をすることが重要です。
飼い主が止めなくてもよいサインの具体的な例は以下の通りです。
- 唸り声や軽い吠えで終わる場合
- 衝突後すぐに犬同士が離れて落ち着く
- 互いに噛む力を調整しており、攻撃が本気でないとき
飼い主が止めるべきけんかと注意点
唸り声や吠えが止まらず、攻撃が繰り返されているときには、犬同士の相性が悪いものと判断し、飼い主が介入する必要があります。
このとき、飼い主が大声を出すと犬がさらに興奮するため、落ち着いて行動することが大切です。
飼い主が咬傷を負うリスクもありますが、犬に対して暴力をふるってはいけません。
犬たちの間に物を入れる、仕切りを使うなどの方法で、物理的に犬同士を引き離します。
犬同士の体格差や力の差が大きい場合は、早めに介入し、それぞれがケガをしないようにしましょう。
このとき、飼い主が大声を出すと犬がさらに興奮するため、落ち着いて行動することが大切です。
飼い主が咬傷を負うリスクもありますが、犬に対して暴力をふるってはいけません。
犬たちの間に物を入れる、仕切りを使うなどの方法で、物理的に犬同士を引き離します。
犬同士の体格差や力の差が大きい場合は、早めに介入し、それぞれがケガをしないようにしましょう。
まとめ

人間同士でも相性があるように、犬たちにも相性があります。辛抱強さや嫉妬心の強さにも個体差があり、どうしても仲良くできないケースもあるでしょう。
それでも、犬それぞれのテリトリーを尊重し、飼い主が平等に愛情を注ぐことで、衝突を避けることはできます。
犬たちの心が成長するにつれて、関係が穏やかに変わることもあります。無理に仲良くさせようとせず、それぞれのペースを大切にしながら、長い目で見守っていきましょう。
関連する記事
それでも、犬それぞれのテリトリーを尊重し、飼い主が平等に愛情を注ぐことで、衝突を避けることはできます。
犬たちの心が成長するにつれて、関係が穏やかに変わることもあります。無理に仲良くさせようとせず、それぞれのペースを大切にしながら、長い目で見守っていきましょう。