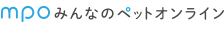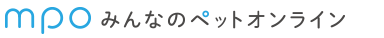犬が食べてはいけないもの~野菜~

ねぎ類(玉ねぎ、長ねぎ、らっきょう、にら、ニンニクなど)
ねぎ類に含まれる香味成分「アリルプロピルジスルフィド」が、赤血球を壊すことで貧血や元気消失といった症状が表れます。生はもちろんですが、加熱処理しても毒性は消失しません。症状が進行すると呼吸困難に陥り、死に至る可能性もあります。
中毒症状が出る目安としては、玉ネギの場合はだいたい1/4個程度、長ねぎは1/3本程度、らっきょうはだいたい1粒といわれています。
にらの中毒を起こす量については明確には解明されていませんが、少量でも絶対に与えないようにしましょう。
中毒症状が出る目安としては、玉ネギの場合はだいたい1/4個程度、長ねぎは1/3本程度、らっきょうはだいたい1粒といわれています。
にらの中毒を起こす量については明確には解明されていませんが、少量でも絶対に与えないようにしましょう。
犬が食べてはいけないもの~果物~

ブドウ、レーズン
中毒症状を起こす成分については現在解明されていませんが、摂取後24時間以内に下痢や嘔吐などの中毒を起こす可能性があります。急性腎不全を起こすと、命に関わることも。
舐めた程度であれば危険性はそれほど高くありませんが、巨峰やマスカットなどの大きいブドウは1粒程度、レーズンは約15粒で症状が出るといわれています。
舐めた程度であれば危険性はそれほど高くありませんが、巨峰やマスカットなどの大きいブドウは1粒程度、レーズンは約15粒で症状が出るといわれています。
アボカド
“森のバター”といわれるほど栄養価の高いことで知られるアボカドですが、「ペルシン」という成分が犬にとっては「毒」となります。
中毒症状を起こす摂取量については、明らかになっていません。少量でも呼吸困難など、重篤な症状を引き起こすこともあるため、注意が必要です。
中毒症状を起こす摂取量については、明らかになっていません。少量でも呼吸困難など、重篤な症状を引き起こすこともあるため、注意が必要です。
柑橘類
柑橘類は、消化に悪い薄皮やすじを取り除いた実だけを与えるのであれば、問題ありません。ただし、まだ未熟の柑橘類に含まれる成分「アルカノイド」により中毒症状につながることもあるので、与える際は熟したものを選んでください。
また、外皮にはワックスが塗られていることもあるので、犬が舐めることがないよう保管場所にも注意が必要です。
また、外皮にはワックスが塗られていることもあるので、犬が舐めることがないよう保管場所にも注意が必要です。
犬が食べてはいけないもの~魚介類~

魚介類(イカ、タコ、エビ、カニ、貝類など)
イカやタコ、エビ、カニ、貝類に含まれる成分「チアミナーゼ」によるビタミンB1欠乏症や、イカに寄生するアニサキスによる食中毒を起こす可能性があります。これらは、加熱することで予防が可能です。
ただし、イカやタコは消化性が悪いため、加熱したものでも胃腸への負担が懸念されます。与える場合はごく少量にし、丸飲みしても問題ないサイズに小さくカットしましょう。
また、カニやエビは、甲殻類アレルギーの原因になる場合があることは覚えておきましょう。アレルギー症状を起こすと、場合によってはアナフィラキシーショックにより死に至る可能性もあります。
人間がカニやエビを食べているときに、甲羅や殻を落としてしまい、犬が誤食してしまうケースもあります。甲羅や殻は、口や消化器官を傷つけることもあるため、気を付けてください。
ただし、イカやタコは消化性が悪いため、加熱したものでも胃腸への負担が懸念されます。与える場合はごく少量にし、丸飲みしても問題ないサイズに小さくカットしましょう。
また、カニやエビは、甲殻類アレルギーの原因になる場合があることは覚えておきましょう。アレルギー症状を起こすと、場合によってはアナフィラキシーショックにより死に至る可能性もあります。
人間がカニやエビを食べているときに、甲羅や殻を落としてしまい、犬が誤食してしまうケースもあります。甲羅や殻は、口や消化器官を傷つけることもあるため、気を付けてください。
犬が食べてはいけないもの~動物性食品~

鶏の骨
鶏の骨は、栄養豊富で成分的にはまったく問題がありません。
しかし、鶏の骨は折れるときに縦に割け、折れ口が鋭くなります。それを犬が食べてしまうと、内臓が傷つく可能性があり、大変危険です。
また、犬には食べ物を丸飲みする習性があるため、大きいままの骨を飲み込んで、のどに詰まらせてしまうという可能性も考えられます。
また、加熱処理をせず生の状態で与えた場合は、サルモネラ菌による食中毒の危険性もあります。
鶏の骨を与える場合は、犬用に加工されたものを選びましょう。ただし、かみ砕く力や消化する力は体格や年齢によって個体差があるので、飼い主の目の届く場所で与えるようにしてください。
しかし、鶏の骨は折れるときに縦に割け、折れ口が鋭くなります。それを犬が食べてしまうと、内臓が傷つく可能性があり、大変危険です。
また、犬には食べ物を丸飲みする習性があるため、大きいままの骨を飲み込んで、のどに詰まらせてしまうという可能性も考えられます。
また、加熱処理をせず生の状態で与えた場合は、サルモネラ菌による食中毒の危険性もあります。
鶏の骨を与える場合は、犬用に加工されたものを選びましょう。ただし、かみ砕く力や消化する力は体格や年齢によって個体差があるので、飼い主の目の届く場所で与えるようにしてください。
生の卵白
卵白に含まれる成分「アビジン」がビオチンの吸収を妨げることによって、ビオチン欠乏症が引き起こされ、皮膚炎や脱毛などの症状が表れる可能性があります。また、サルモネラ菌による食中毒を起こすことも。
アビジンは、大量摂取や日常的に与えることで影響が大きくなります。
しかし、黄身にはビオチンが大量に含まれているため、全卵であれば生卵を食べても大丈夫といわれています。
ただし、生卵を与える場合は、新鮮な卵をあげるようにし、食べ残しは速やかに片付けましょう。
また、アビジンは熱に弱いため、加熱すれば白身単体であげても問題ありません。
卵は栄養豊富ですが、与える際はおやつ程度に留め、あげすぎには注意しましょう。1日に与える量は小型犬で多くても1/3個程度にしてください。
そのほかにも、人と同じように卵アレルギーに注意が必要です。
アビジンは、大量摂取や日常的に与えることで影響が大きくなります。
しかし、黄身にはビオチンが大量に含まれているため、全卵であれば生卵を食べても大丈夫といわれています。
ただし、生卵を与える場合は、新鮮な卵をあげるようにし、食べ残しは速やかに片付けましょう。
また、アビジンは熱に弱いため、加熱すれば白身単体であげても問題ありません。
卵は栄養豊富ですが、与える際はおやつ程度に留め、あげすぎには注意しましょう。1日に与える量は小型犬で多くても1/3個程度にしてください。
そのほかにも、人と同じように卵アレルギーに注意が必要です。
牛乳
犬は「乳糖」という成分を分解する酵素が少ないため、下痢や嘔吐といった消化器官のトラブルを起こすことがあります。また、牛乳はアレルギーや肥満の原因にもなります。
水分補給として水代わりに与えるのは、おすすめできません。あくまで食事の補助と考え、与える量は1日10g程度にとどめましょう。
水分補給として水代わりに与えるのは、おすすめできません。あくまで食事の補助と考え、与える量は1日10g程度にとどめましょう。
ハム、ソーセージ
ハムやソーセージといった加工肉は塩分や脂質が多く、添加物も含まれています。人間用として作られた食品であるため、摂取量が多いと犬の体には大きな負担をかけます。
少量であれば緊急性のある症状が出ることはほとんどありませんが、積極的に与えるのは避けたほうがよいでしょう。
少量であれば緊急性のある症状が出ることはほとんどありませんが、積極的に与えるのは避けたほうがよいでしょう。
レバー
レバーは鉄分豊富なイメージが強いと思いますが、ビタミンAも多く含まれている食材です。ビタミンAは皮膚や粘膜を丈夫にしてくれる重要な成分ですが、実は過剰に摂取すると健康障害を起こしてしまう可能性があるのです。
主食のトッピングとして与える程度にしましょう。
また、生の状態のレバーは、病原体による食中毒や寄生虫感染のリスクが非常に高くなるので絶対に与えてはいけません。
しっかり加熱処理したものを与え、傷みやすいので鮮度にも気を付けましょう。
主食のトッピングとして与える程度にしましょう。
また、生の状態のレバーは、病原体による食中毒や寄生虫感染のリスクが非常に高くなるので絶対に与えてはいけません。
しっかり加熱処理したものを与え、傷みやすいので鮮度にも気を付けましょう。
犬が食べてはいけないもの~そのほかの危険物~

チョコレート、ココア
チョコレートとココアの原料であるカカオに含まれる成分「テオブロミン」が、中毒症状を起こします。初期症状としては下痢や嘔吐、進行すると死に至る可能性があります。
チョコレートの種類にはダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートなどがありますが、カカオ濃度が高いダークチョコレートがもっとも危険性が高くなります。
中毒症状を起こす摂取量はホワイトチョコレートが犬の体重1kgに対し約500g、ダークチョコレートは体重1㎏に対しわずか5gほど。
チョコレートの種類によって、症状を引き起こす量が異なるため注意が必要です。
チョコレートの種類にはダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレートなどがありますが、カカオ濃度が高いダークチョコレートがもっとも危険性が高くなります。
中毒症状を起こす摂取量はホワイトチョコレートが犬の体重1kgに対し約500g、ダークチョコレートは体重1㎏に対しわずか5gほど。
チョコレートの種類によって、症状を引き起こす量が異なるため注意が必要です。
キシリトール
犬がキシリトール入りの歯磨き粉やガムなどを誤食してしまう事故が報告されています。また、キシリトールは甘味料として、食品に使用されていることもあるので、注意が必要です。
キシリトールは、体重1kgに対しおよそ0.1gで低血糖や嘔吐などの中毒を起こす可能性があり、一般的な市販のガム1粒程度というわずかな量でも、急性肝不全になる場合もあります。
キシリトールは、体重1kgに対しおよそ0.1gで低血糖や嘔吐などの中毒を起こす可能性があり、一般的な市販のガム1粒程度というわずかな量でも、急性肝不全になる場合もあります。
マカダミアナッツ
ナッツ類のなかには犬が中毒を起こさない種類もありますが、マカダミアナッツは嘔吐や腹痛といった中毒症状を引き起こします。
原因物質ついては解明されていませんが、3粒ほど食べると症状が出るといわれています。
原因物質ついては解明されていませんが、3粒ほど食べると症状が出るといわれています。
銀杏
銀杏には「ギンコトキシン(メチルピリドキシン)」という神経毒の一種が含まれています。
中毒を起こす摂取量については個体差があり、なかには1粒食べただけで呼吸困難などの重い症状が出る犬も。
銀杏の独特なにおいが犬の興味を引くこともあるため、散歩中の拾い食いに気を付けてください。銀杏がなる秋ごろは、イチョウの木がある場所は散歩コースから外してもよいでしょう。
中毒を起こす摂取量については個体差があり、なかには1粒食べただけで呼吸困難などの重い症状が出る犬も。
銀杏の独特なにおいが犬の興味を引くこともあるため、散歩中の拾い食いに気を付けてください。銀杏がなる秋ごろは、イチョウの木がある場所は散歩コースから外してもよいでしょう。
アルコール
犬にはアルコールに含まれる「エタノール」を分解する酵素をもたないため、下痢や嘔吐、昏睡といった中毒症状を起こします。
症状が表れる摂取量は明らかになっていませんが、少し舐めたという程度で中毒になることも……。
アルコール飲料に加え、ウエットティッシュや除菌スプレーなどアルコールが含まれるものの扱いにも気を付けましょう。
症状が表れる摂取量は明らかになっていませんが、少し舐めたという程度で中毒になることも……。
アルコール飲料に加え、ウエットティッシュや除菌スプレーなどアルコールが含まれるものの扱いにも気を付けましょう。
カフェイン
コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、下痢や嘔吐のほか、興奮といった症状を起こします。
小型犬の場合は、コップ1杯の緑茶が致死量に達するともいわれています。犬は人間よりもカフェインに対する感受性が非常に高いため、少量でも危険です。
また、飲みもの以外にも、コーヒーや紅茶が使われたお菓子にもカフェインは含まれているため注意が必要です。
小型犬の場合は、コップ1杯の緑茶が致死量に達するともいわれています。犬は人間よりもカフェインに対する感受性が非常に高いため、少量でも危険です。
また、飲みもの以外にも、コーヒーや紅茶が使われたお菓子にもカフェインは含まれているため注意が必要です。

人の食べ物はワンちゃんが届かない場所にしまいましょう
原田 友紀先生
「あげたらダメだと知らずにあげてしまった」というケースもありますが、それよりも「ちょっと目を離したすきに食べてしまった」、「床に落ちていたものを食べてしまった」というような、ちょっとした不注意から口にしてしまうケースが多いです。
ワンちゃんが食べてはいけないものは、普段からワンちゃんの手の届かないところに置く、きちんと掃除をするなど、ワンちゃんが口にしないよう注意しましょう。
ワンちゃんが食べてはいけないものは、普段からワンちゃんの手の届かないところに置く、きちんと掃除をするなど、ワンちゃんが口にしないよう注意しましょう。
犬が中毒になっているときの症状

誤食や過剰摂取による中毒にはさまざまな症状があり、それが重篤な症状の前兆となることもあります。
嘔吐
中毒症状として多く見られるのが、嘔吐。早食いや食べ過ぎによる胃腸の過剰反応という可能性もありますが、中毒の初期症状や中毒により別の病気に進行しているサインの場合もあるため注意が必要です。
たとえば、キシリトール中毒を起こした場合、「中毒の初期症状としての嘔吐」と「中毒による急性肝不全の前兆の嘔吐」の2つの可能性があるということです。
嘔吐の症状を起こしやすい食べ物には、以下のようなものがあげられます。
嘔吐による脱水症状にも気を付けましょう。
たとえば、キシリトール中毒を起こした場合、「中毒の初期症状としての嘔吐」と「中毒による急性肝不全の前兆の嘔吐」の2つの可能性があるということです。
嘔吐の症状を起こしやすい食べ物には、以下のようなものがあげられます。
- チョコレート、ココア
- ブドウ、レーズン
- アボカド
- マカダミアナッツ
- 銀杏
- 鶏の骨
- アルコール
- カフェイン
- 牛乳
- 柑橘類
嘔吐による脱水症状にも気を付けましょう。
下痢
嘔吐と同様、下痢もまた中毒としてよく見られる症状の1つです。下痢は脱水症状を誘発するため、回数が多いときはとくに注意してください。
下痢の症状を起こしやすい食べ物には、以下のようなものがあげらます。
下痢の症状を起こしやすい食べ物には、以下のようなものがあげらます。
- チョコレート、ココア
- ブドウ、レーズン
- アボカド
- マカダミアナッツ
- アルコール
- 鶏の骨
- カフェイン
- イカ、タコ
- 牛乳
- カニ、エビ
- 柑橘類
元気消失
ほかの中毒症状の前兆、あるいは症状が軽い場合に見られます。たとえばぶどう、レーズン中毒による急性腎不全時、マカダミアナッツ中毒により腹痛が起きている場合などです。目立たない症状なため、気付かないこともあるので注意が必要です。
<中毒時元気消失が見られる食べ物>
<中毒時元気消失が見られる食べ物>
- ねぎ類
- ブドウ、レーズン
- キシリトール
- マカダミアナッツ
- 銀杏
- 鶏の骨
- 魚介類(イカ、タコ、カニ、エビ、貝類) など
けいれん
けいれんを起こす可能性があるのは、銀杏や柑橘類、また、チョコレートやココアは中毒症状が進行した場合、アルコールは重度の中毒症状、キシリトール中毒時の低血糖、ブドウ中毒時の急性腎不全の場合に表れます。
ほかの食べ物でも、アレルギー反応によるアナフィラキシーショックで、けいれんを起こす可能性もあります。
ほかの食べ物でも、アレルギー反応によるアナフィラキシーショックで、けいれんを起こす可能性もあります。
貧血
ねぎ類に含まれる「アリルプロピルジスルフィド」という成分が赤血球を破壊し、貧血症状を起こします。
軽度であると飼い主が気付かないことがありますが、症状が進むと呼吸困難を起こし、死に至る可能性もあります。
軽度であると飼い主が気付かないことがありますが、症状が進むと呼吸困難を起こし、死に至る可能性もあります。
血便
鶏の骨などにより腸が傷ついたとき、カフェイン摂取により急性の消化器症状があるときに、血便が出ることがあります。
中毒症状が表れるのにかかる時間
犬の中毒症状は一般的に24時間以内に表れますが、犬の体質や食べ物によっては直後、あるいは数日後ということもあります。
チョコレート、ココア、マカダミアナッツは通常6~12時間以内ですが、早いと1~2時間以内に発症。キシリトールやアルコールは30分~1時間以内と摂取してすぐに症状が出ることが多いようです。
いっぽう、ねぎ類やアボカドなどは1~5日以内と発症までの時間が長いため、誤食した場合にはしばらく注意して観察するのがよいでしょう。
チョコレート、ココア、マカダミアナッツは通常6~12時間以内ですが、早いと1~2時間以内に発症。キシリトールやアルコールは30分~1時間以内と摂取してすぐに症状が出ることが多いようです。
いっぽう、ねぎ類やアボカドなどは1~5日以内と発症までの時間が長いため、誤食した場合にはしばらく注意して観察するのがよいでしょう。

ワンちゃんが何かを食べたかを把握しておくことがカギ
原田 友紀先生
症状のみで中毒か中毒以外の原因によるものか判断することは難しく、ワンちゃんが中毒を起こすものを食べた可能性があるかどうかが、中毒を疑うポイントの一つになります。
嘔吐などの症状が一度のみでなく繰り返し見られる場合や、複数の症状が見られる場合には、中毒やほかの原因で体調を崩している可能性もあるため、かかりつけの先生に相談しましょう。
嘔吐などの症状が一度のみでなく繰り返し見られる場合や、複数の症状が見られる場合には、中毒やほかの原因で体調を崩している可能性もあるため、かかりつけの先生に相談しましょう。
犬が中毒になっているときの対処法

愛犬が食べてはいけないものを食べてしまった、あるいはすでに中毒症状が出ているとき、どのような対処を取るべきか解説します。
自宅での対処法
どれくらい食べたか確認する
犬の体重と食べた量を把握することで、症状が軽度なのか重度なのかの判断に結び付きます。
紹介した食べ物以外でも食べすぎにより中毒を起こすこともあるため、気になる様子があるときは大量に食べたものがないか、確認してみましょう。
紹介した食べ物以外でも食べすぎにより中毒を起こすこともあるため、気になる様子があるときは大量に食べたものがないか、確認してみましょう。
病院に相談する
犬の中毒を飼い主が治療することはできません。できるだけ早く動物病院に連絡し、獣医師からの指示を仰ぎましょう。
獣医師に伝えることは、いつ・何を・どれくらい食べたのかという3点です。また、愛犬の様子で気になることがあれば、できるだけ細かく正確に伝えると診察に役立ちます。
言葉で説明が難しい場合は、動画や写真を撮っておくとよいでしょう。
獣医師に伝えることは、いつ・何を・どれくらい食べたのかという3点です。また、愛犬の様子で気になることがあれば、できるだけ細かく正確に伝えると診察に役立ちます。
言葉で説明が難しい場合は、動画や写真を撮っておくとよいでしょう。
自己判断で催吐処置をしない
愛犬の誤食や中毒に気付いたとき、「とりあえず、食べたものを吐かせなければ」と思う飼い主は少なくないかもしれません。しかし、獣医師の判断なしに自宅で催吐処置をおこなうのはとても危険です。
無理に吐かせることで、気管を詰まらせるなど命の危険にさらす可能性もあります。
食べ物の種類や症状によっては、催吐処置をおこなわないほうがよいこともあるので、自己判断せず、必ず獣医師の診察を受けましょう。
無理に吐かせることで、気管を詰まらせるなど命の危険にさらす可能性もあります。
食べ物の種類や症状によっては、催吐処置をおこなわないほうがよいこともあるので、自己判断せず、必ず獣医師の診察を受けましょう。
病院でおこなわれる処置
催吐処置
誤食をしてそれほど時間が経過しておらず、胃の中に毒素である成分が残っている可能性がある場合は、注射などの薬を使って吐き戻しをさせます。
対症療法
誤食をしてから時間が経過しており、体内に毒素が回ってしまっているときには、点滴で毒素の濃度を薄める処置をおこないます。
また、毒素を体内で吸着し排出する効果のある飲み薬の投与をすることも。
すでに症状が出ている場合には、症状に合わせた治療をおこないます。
また、毒素を体内で吸着し排出する効果のある飲み薬の投与をすることも。
すでに症状が出ている場合には、症状に合わせた治療をおこないます。
胃洗浄
催吐処置をしても嘔吐してくれない、中毒が致死レベルの緊急性が高い場合などにおこないます。ただし、これは胃に毒物が残っている場合に限り有効な対処法です。
犬の状態や食べたものによって処置の方法は異なります。獣医師の判断に任せましょう。
犬の状態や食べたものによって処置の方法は異なります。獣医師の判断に任せましょう。

「いつ」「何を」「どのくらいの量」を確認しましょう。
原田 友紀先生
ワンちゃんが食べてはいけないものを食べてしまった場合、まずは「いつ」「何を」「どのくらいの量」食べてしまったか確認しましょう。それにより、様子を見てもよさそうなのか、なにか処置や検査が必要か、必要ならどのような処置や検査をするか、変わります。
もしもワンちゃんに症状があるなら、いつから、どのような症状が、どのくらいの頻度で見られるのかもチェックしておくと、すでに中毒を起こしてしまっている可能性が高いか、判断するのに役立ちます。
もしもワンちゃんに症状があるなら、いつから、どのような症状が、どのくらいの頻度で見られるのかもチェックしておくと、すでに中毒を起こしてしまっている可能性が高いか、判断するのに役立ちます。
獣医師に聞いた! 犬が食べたら危険なものについてのQ&A
犬が誤って食べると危険な食べ物を食べてしまった! 体調に変化がなくても病院に行くべき?
ワンちゃんが食べると危険なものを食べてしまった場合、食べた物の量やワンちゃんの体格によっては中毒が出ずに済んでくれることもあります。
しかし、中毒を起こす物質に対してどのくらい反応しやすいかというのはワンちゃんによって個体差もありますし、中毒の症状が出るまでに数日かかったり、症状が出てから治療しても間に合わない場合、治療に時間がかかってしまう場合もあります。
誤飲したことに気付いた時点で病院に相談するのがよいでしょう。
しかし、中毒を起こす物質に対してどのくらい反応しやすいかというのはワンちゃんによって個体差もありますし、中毒の症状が出るまでに数日かかったり、症状が出てから治療しても間に合わない場合、治療に時間がかかってしまう場合もあります。
誤飲したことに気付いた時点で病院に相談するのがよいでしょう。
ニンニクは犬にあげちゃいけないのに、ドッグフードにニンニクが入っていることがある。大丈夫なの?
人にとってニンニクが体によい食べ物であるように、ワンちゃんにとってもニンニクに含まれている成分が健康によいのではないかという報告もあり、ドッグフードにニンニクを入れることもあるようです。
その場合でも、中毒を起こすといわれている量よりもかなり少ない量であることがほとんどです。
ただ、中毒を起こす量は個体差もあるため、心配であればあげないようにするのがよいでしょう。
その場合でも、中毒を起こすといわれている量よりもかなり少ない量であることがほとんどです。
ただ、中毒を起こす量は個体差もあるため、心配であればあげないようにするのがよいでしょう。
犬が食べてはいけないものを食べたがる。少しなら大丈夫?
ワンちゃんは、飼い主が食べているものに興味を示して食べたがることもあります。ただ、ワンちゃんはそれが食べてもよいものなのか、食べると危険なものか、自分では判断できないため、飼い主が気を付ける必要があります。
ワンちゃんが食べてはいけないものは、おねだりされてもあげないようにしましょう。
ワンちゃんが食べてはいけないものは、おねだりされてもあげないようにしましょう。
獣医師からのメッセージ
ワンちゃんの誤食を防ぐには、普段からの対策が大切です。ワンちゃんが食べると危険なものをワンちゃんの届くところに置かない、キッチンなど危険なものがたくさんある場所にはワンちゃんが入れないようにする、などです。
届かないだろう、と思っても、何かの拍子に落ちてしまったり、ジャンプしたり椅子に登ったりすることで届いてしまう、ということもあるため、注意が必要です。
また、ワンちゃんにあげてよい食べ物であっても、アレルギーを起こしたりおなかに合わなかったりすることもあります。
そのほかに病気のあるワンちゃんには控えたほうがよい食べ物もあるので、ワンちゃんに人の食べ物をあげる際には、慎重にあげるようにしましょう。
届かないだろう、と思っても、何かの拍子に落ちてしまったり、ジャンプしたり椅子に登ったりすることで届いてしまう、ということもあるため、注意が必要です。
また、ワンちゃんにあげてよい食べ物であっても、アレルギーを起こしたりおなかに合わなかったりすることもあります。
そのほかに病気のあるワンちゃんには控えたほうがよい食べ物もあるので、ワンちゃんに人の食べ物をあげる際には、慎重にあげるようにしましょう。
まとめ

犬と暮らすうえでは、犬が食べてはいけないものを覚えておくことが大切です。万が一危険な食べ物を口にしてしまったら、自己判断せずに獣医師に相談しましょう。「いつ」「何を」「どのくらい」食べてしまったのか、可能な範囲で確認しておくと診断の助けになります。
一番大切なのは、犬が届くところに食べ物を置かないことです。事故が起きないように、できるだけ危険を減らし、愛犬との生活を楽しんでくださいね。
一番大切なのは、犬が届くところに食べ物を置かないことです。事故が起きないように、できるだけ危険を減らし、愛犬との生活を楽しんでくださいね。