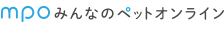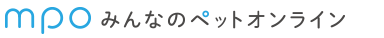犬の熱中症が疑われる症状

熱中症の主な症状 初期~中期
下記のような症状がみられたら熱中症の初期または中期の状態かもしれません。
- いつもより激しくパンディング(口を大きく開け、ハァハァと息を出す特有の口呼吸)をしている
- 嘔吐する
- 下痢をする
- 体温が上昇する(40℃以上)
- 食欲がなくなる、水を飲もうとしない
- 過度に水を欲しがる
- ぼぉーっとしている、足元がふらついている
- 横たわってグッタリしている
熱中症の重篤なケース
下記のような症状は重症化が考えられ、一刻を争います。
このような症状がみられたら、体を冷やす処置をしつつ病院へ連絡し、できるだけ早く受診しましょう。
また、症状の重度にかかわらず、熱中症が疑われるような症状が見られた場合には速やかに病院へ連れていくことをおすすめします。
- 歯茎が白くなる
- 舌や口の中が青紫色になる
- 震えやけいれんがある
- 嘔吐する
- 声をかけても反応がない、意識がなくなる
このような症状がみられたら、体を冷やす処置をしつつ病院へ連絡し、できるだけ早く受診しましょう。
また、症状の重度にかかわらず、熱中症が疑われるような症状が見られた場合には速やかに病院へ連れていくことをおすすめします。

温度、湿度、直前の様子などから診断
原田 友紀先生
夏場に上記症状の発症と高体温が確認されている状況では、熱中症を強く疑います。
犬が生活する高さ(体高)での温度調整ができているか、湿度は高くないかといった生活環境や症状が出る直前にどんなことをしていたかどんな様子だったのか、前日~当日の朝方の様子などを聞きながら診断を進めていきます。
犬が生活する高さ(体高)での温度調整ができているか、湿度は高くないかといった生活環境や症状が出る直前にどんなことをしていたかどんな様子だったのか、前日~当日の朝方の様子などを聞きながら診断を進めていきます。
犬の熱中症の原因

犬も人間と同じように熱中症になります。
何が原因で起こるのでしょう。最悪の事態になる前に気付くことはできるのでしょうか。
発症の原因としてよくあるケースを解説します。
何が原因で起こるのでしょう。最悪の事態になる前に気付くことはできるのでしょうか。
発症の原因としてよくあるケースを解説します。
密室状態の車の中にいた
猛暑日でなく、長時間の放置でもなく、完全密室ではなくても、夏の車内は熱中症リスクがかなり高いです。
車内は想像以上に高温になります。たとえ短時間でも犬を車内で待たせることのないようにしましょう。窓を少し開けていたくらいでは、対策にはなりません。
車内は想像以上に高温になります。たとえ短時間でも犬を車内で待たせることのないようにしましょう。窓を少し開けていたくらいでは、対策にはなりません。

日中気温の高い時間帯に外で散歩や運動をしていた
私たちは靴を履き、背丈があるため気付きにくいですが、日中気温の高い時間帯は地面からの照り返しも強く、危険です。
高温のなか散歩や運動などで体を動かし興奮状態にさせるのは熱中症発症リスクが高いだけでなく、高温のアスファルトによる肉球やけどの危険もあります。
また、日中の温度に気を取られがちですが、日没直後も注意が必要です。
日没直後はまだアスファルトが冷めきっておらず、輻射熱により、熱中症になるリスクがあります。
散歩に出る前に一度アスファルトの温度を確認しましょう。
高温のなか散歩や運動などで体を動かし興奮状態にさせるのは熱中症発症リスクが高いだけでなく、高温のアスファルトによる肉球やけどの危険もあります。
また、日中の温度に気を取られがちですが、日没直後も注意が必要です。
日没直後はまだアスファルトが冷めきっておらず、輻射熱により、熱中症になるリスクがあります。
散歩に出る前に一度アスファルトの温度を確認しましょう。
日の当たるところにケージやサークルを置いていた
意外に見落としがちなのが直射日光の入り込む場所です。
ケージやサークルを日が当たる場所に設置していたために、なかで過ごしていた愛犬が熱中症にかかっていた、という事例は多いです。
室内外を問わず、日が差し込む場所は把握しておきましょう。
ケージやサークルを日が当たる場所に設置していたために、なかで過ごしていた愛犬が熱中症にかかっていた、という事例は多いです。
室内外を問わず、日が差し込む場所は把握しておきましょう。
暑い日に冷房をつけないで室内で留守番をさせた
朝、飼い主さんの外出時はそれほど暑くなかったからという理由で、冷房をつけずに留守番をさせてしまった場合です。
飼い主さんが帰宅したら愛犬がグッタリしていたというケースがもっとも多いといわれています。
夏は午前中や夕方でも、締め切った室内の気温は高くなります。1日を通しての気温を確認するとともに、外の気温と室内温度の違いにも気を配る必要があります。
飼い主さんが帰宅したら愛犬がグッタリしていたというケースがもっとも多いといわれています。
夏は午前中や夕方でも、締め切った室内の気温は高くなります。1日を通しての気温を確認するとともに、外の気温と室内温度の違いにも気を配る必要があります。
海やバーベキューに連れて行き、屋外で過ごさせていた
真夏日の屋外は、風があっても、屋根やパラソルの下にいたとしても、危険です。
人間が問題なく過ごせる状況でも、厚い被毛をまとい、地面からの照り返しを強く受けている犬には通じません。
人間が問題なく過ごせる状況でも、厚い被毛をまとい、地面からの照り返しを強く受けている犬には通じません。
愛犬に熱中症の疑いがあるとき、すぐにできる応急処置

熱中症とは、体温が高い状態と脱水症状が続いたことにより生じる、全身性の疾患です。
発症すると臓器の機能に障害が出始めるため、命を奪われてしまうこともあります。
もし愛犬が熱中症にかかってしまったら……。応急処置が命を救うことになるでしょう。
ここでは、熱中症初期の応急処置方法をご紹介します。
発症すると臓器の機能に障害が出始めるため、命を奪われてしまうこともあります。
もし愛犬が熱中症にかかってしまったら……。応急処置が命を救うことになるでしょう。
ここでは、熱中症初期の応急処置方法をご紹介します。
1.涼しいところに移動させる
屋外の場合、日陰や涼しいところに移動させます。室内であればエアコンをつけたり、風を送ったりして体を冷やします。
2.濡らしたタオルで体を包む
濡れたタオルで体を包み、風をあててあげましょう。
保冷剤や氷は冷えすぎや凍傷、急激な体温低下に伴うショックなどの危険があるため、濡れたタオルで体を冷やしてあげるのがおすすめです。
もし、保冷剤や氷しかない場合は、必ずタオルなどで包んで使用し、直接犬の体に保冷剤や氷が当たらないようにしましょう。
保冷剤や氷は冷えすぎや凍傷、急激な体温低下に伴うショックなどの危険があるため、濡れたタオルで体を冷やしてあげるのがおすすめです。
もし、保冷剤や氷しかない場合は、必ずタオルなどで包んで使用し、直接犬の体に保冷剤や氷が当たらないようにしましょう。

3.水を飲ませる
水を飲めそうなら飲ませます。スポーツドリンクを水で薄めたものもよいでしょう。 どうしても飲まなければ、無理に飲ませる必要はありません。
愛犬の様子が落ち着いたら動物病院に連絡をし、受診の必要があるかどうかなど、指示を仰いでください。
愛犬の様子が落ち着いたら動物病院に連絡をし、受診の必要があるかどうかなど、指示を仰いでください。
4.犬の体に水をかける
シャワーや水道が近くにある、ペットボトルの水を持っているなどの場合は、犬の体に直接水をかけてあげるのも効果的です。エアコンや扇風機がつけられる状況でなければ、あり物で扇ぐなどして風を送ってあげるとよいでしょう。
応急処置を終えたら、動物病院に連絡します。状況、症状を説明したうえで、応急処置として今できることを確認しましょう。その後は体を冷やしつつ、病院へ連れて行くことをおすすめします。
体を冷やしすぎてもいけない
熱中症の場合、「体を冷やすことが大切」とご紹介してきました。しかし実は「冷やしすぎ」にも注意が必要です。
体を冷やしすぎると、今度は犬の体が低体温状態に陥ってしまうのです。
動物病院では、肛門で熱を測る「直腸温」が39.5℃に下がったら、体を冷やす処置はいったん停止することが多いようです。
体を触って冷たくなりすぎていないか確認するようにしましょう。
体を冷やしすぎると、今度は犬の体が低体温状態に陥ってしまうのです。
動物病院では、肛門で熱を測る「直腸温」が39.5℃に下がったら、体を冷やす処置はいったん停止することが多いようです。
体を触って冷たくなりすぎていないか確認するようにしましょう。

極端に冷たいものの使用に注意
原田 友紀先生
体を冷やすときにはショックや低体温のリスクが伴うため、氷水や極端に冷たい水を用いることは控えましょう。
どうしても保冷材や氷などしかない場合には、タオルなどで覆い接触面が冷えすぎないように注意しましょう。
また、体に水をかけて冷やす際には気管に水が入らないよう注意が必要です。
どうしても保冷材や氷などしかない場合には、タオルなどで覆い接触面が冷えすぎないように注意しましょう。
また、体に水をかけて冷やす際には気管に水が入らないよう注意が必要です。
熱中症になりやすい犬

全身で汗をかけず、口呼吸で体温調節をおこなっている犬は基本的に暑さに弱い動物です。
そのなかでも、より暑さが苦手で、熱中症になりやすいタイプの犬がいます。
そのなかでも、より暑さが苦手で、熱中症になりやすいタイプの犬がいます。
循環器、泌尿器などに疾患がある、脱水しやすい犬
循環器は飲水制限がかかることも多く、気軽に水を飲ませられないことも熱中症のリスク要因となります。
短頭種
短頭種といわれる犬種は、口腔の面積が狭いため口から熱を逃がすのが苦手です。
夏場は体温調節がうまくできず、熱中症になりやすいといえます。
※『みんなのブリーダー』の子犬検索ページに遷移します
夏場は体温調節がうまくできず、熱中症になりやすいといえます。
※『みんなのブリーダー』の子犬検索ページに遷移します
寒冷地原産の犬
原産地が寒冷な地域の犬は、防寒効果の高い分厚い被毛をまとっています。
夏には夏用の毛に生え変わりますが、それでも長く豊富な被毛には熱がこもりやすく、高体温になりやすい犬種といえるでしょう。
夏には夏用の毛に生え変わりますが、それでも長く豊富な被毛には熱がこもりやすく、高体温になりやすい犬種といえるでしょう。
肥満気味の犬
皮下脂肪が多いと体内の熱が外に逃れにくく、熱中症リスクは高まります。
また、首回りに脂肪がつくことで、呼吸がしにくくなってしまうことも熱中症のリスクを高めてしまいます。
また、首回りに脂肪がつくことで、呼吸がしにくくなってしまうことも熱中症のリスクを高めてしまいます。
子犬やシニア犬
子犬は体が小さく、未発達器官が多いことから、シニア犬は老化による機能低下から、体温調節がスムーズではありません。体力がないことでもリスクは高まります。
犬の暑さ対策

暑い季節、どのようにすれば愛犬が安全に過ごすことができるのか、犬のための暑さ対策を考えましょう
犬にとって快適な温度とは
室内の温度は25℃前後、湿度は50%前後が、犬が快適で安全に過ごせる目安です。
しかし、熱中症になりやすい犬種のなかには25℃では暑がる様子を見せることも。
愛犬の様子をよく観察し、暑がっているようであれば、エアコンの設定温度を下げるなどして、室温を調整しましょう。
しかし、熱中症になりやすい犬種のなかには25℃では暑がる様子を見せることも。
愛犬の様子をよく観察し、暑がっているようであれば、エアコンの設定温度を下げるなどして、室温を調整しましょう。
室内環境を整える
基本的にはエアコンを使いましょう
地域によって違いはありますが、熱帯夜が続く1カ月くらいは、エアコンはつけっぱなしという家庭も珍しくなくなってきました。出かける際も犬を留守番させるときは、エアコンは切らずにおきましょう。
ケージの置き場所を考える
ケージやサークルなど留守番時に愛犬が長い時間過ごす場所は、直射日光とエアコンからの風が直接当たらない場所に設置します。
ひんやりグッズを用意する
ひんやりマットや遮光レースカーテンなど、室内の温度を下げる効果のあるグッズがたくさん出ています。活用してみましょう。
水分補給ができるようにする
夏場は水の摂取量がぐんとあがります。
帰ってきたら水入れがカラだったということがないように、容器を大きくする、水場を2カ所以上作るなどの対策をとりましょう。
帰ってきたら水入れがカラだったということがないように、容器を大きくする、水場を2カ所以上作るなどの対策をとりましょう。

散歩やおでかけ時の暑さ対策
散歩は朝晩の涼しい時間帯に行く
毎日の散歩を涼しい時間帯に行くというのは、暑さ対策でもっとも重要なもののひとつです。
しかし7~8月は涼しい時間帯が短いため、調整が難しいかもしれません。
生活サイクルを見直し、スケジュールの見直しを検討してみましょう。
具体的には、7月8月の朝7時はすでに暑くなりはじめ、何かと朝の準備で忙しい時間帯でもあります。散歩はそれより前の5~6時台をおすすめします。
5時というと非常に早く感じるかもしれません。しかし実際は、たくさんの人が散歩やジョギングをしている快適な時間帯といえます。
日中50℃を超えたアスファルトが30℃まで下がるのは22時以降だといわれています。夜の散歩はその頃がベストです。
仕事などの都合で調整が難しい日は、朝か夜どちらかの散歩を長めにする、室内での運動時間を多めに設けるなどの対策をとるといいでしょう。
しかし7~8月は涼しい時間帯が短いため、調整が難しいかもしれません。
生活サイクルを見直し、スケジュールの見直しを検討してみましょう。
具体的には、7月8月の朝7時はすでに暑くなりはじめ、何かと朝の準備で忙しい時間帯でもあります。散歩はそれより前の5~6時台をおすすめします。
5時というと非常に早く感じるかもしれません。しかし実際は、たくさんの人が散歩やジョギングをしている快適な時間帯といえます。
日中50℃を超えたアスファルトが30℃まで下がるのは22時以降だといわれています。夜の散歩はその頃がベストです。
仕事などの都合で調整が難しい日は、朝か夜どちらかの散歩を長めにする、室内での運動時間を多めに設けるなどの対策をとるといいでしょう。
水を持ち歩いて水分補給をさせる
いつもの散歩コースでも、水や保冷剤を持ち歩くようにしましょう。散歩中の給水タイムは愛犬が興奮しすぎているときのクールダウンにも役立ちます。
機能的でおしゃれな犬用の給水ボトルや、ペットボトルに取り付ける給水グッズが市販されています。
機能的でおしゃれな犬用の給水ボトルや、ペットボトルに取り付ける給水グッズが市販されています。
保冷剤やひんやりタオルを持ち歩く
ペット用の保冷剤やひんやりタオルが市販されています。犬用ジャケットやバンダナに、保冷剤を入れられるタイプもあるようです。

犬を車内に置いていかない
犬を車内に置いていくのは、ほんの少しの時間でも危険です。車内での熱中症は夏場に限らず、春先や秋にも報告されています。外気温が20~25℃という過ごしやすい日であっても、車の中が40℃以上になることは珍しくないのです。
犬にも紫外線対策は必要
犬も人間と同じように、紫外線を浴び続けることによって皮膚炎や皮膚がんなどの発症リスクが高まります。とくに短毛種やシングルコートの犬は紫外線が苦手です。
UVカット機能のある服や日焼け止めスプレーなど、UVグッズで対策をおこないましょう。
関連する記事
UVカット機能のある服や日焼け止めスプレーなど、UVグッズで対策をおこないましょう。
犬の暑さ対策グッズ

熱中症対策にたくさんの便利グッズが出ています。
どのようなものがあるか、使用の際の注意点もあわせてご紹介します。
どのようなものがあるか、使用の際の注意点もあわせてご紹介します。
おすすめのひんやりグッズ
冷感マット
大理石、アルミ、布製、ジェルタイプなどさまざまな種類があり、冷暖切り替え可能な家電タイプも発売されています。
丈夫なもの、洗えるもの、汚れを拭き取れるものが便利です。
丈夫なもの、洗えるもの、汚れを拭き取れるものが便利です。
冷感ウェア
冷感効果のある素材で作られたベストタイプの洋服や、保冷剤入れポケット付きのもの、濡らして使うバンダナタイプなどがあります。
クールミスト
ミントやティーツリーなどが配合された、クールダウン効果のあるスプレーが売られています。
購入前に注意書きを読み、使用に不安がある方は獣医師に相談しましょう。
購入前に注意書きを読み、使用に不安がある方は獣医師に相談しましょう。
携帯用ウォーターボトル
ボトルに水皿が付いているもの、ペットボトルの口にセットするものなどさまざまな種類があります。
洗いやすく、乾きやすいものが便利です。
洗いやすく、乾きやすいものが便利です。
熱中症計
気温と湿度を設定すると、危険レベルを警報音で知らせてくれる計測器です。
リードやバッグに装着できるもの、人間用としても使えるものもあり、大きさや機能もさまざまです。
リードやバッグに装着できるもの、人間用としても使えるものもあり、大きさや機能もさまざまです。
扇風機、サーキュレーター
換気や空気の循環、エアコンの効率化をはかるために使用します。

プール
犬用は、空気を入れるタイプではなく、折り畳み式で丈夫に作られています。
与えればいいというものではない? 注意して利用したいグッズ
保冷剤
誤飲のおそれがあるため、飼い主さんの目の届く範囲内で使用しましょう。与えっぱなしは危険です。
とくに、多くの保冷材に使われている「エチレングリコール」という成分は中毒性が高いので気を付けましょう。
とくに、多くの保冷材に使われている「エチレングリコール」という成分は中毒性が高いので気を付けましょう。
扇風機だけでは涼しくならない?
室内温度が高い場合、扇風機を回すだけでは不十分です。
真夏日は、エアコンの効率化をはかるサーキュレーターのような使い方をするのがよいでしょう。
真夏日は、エアコンの効率化をはかるサーキュレーターのような使い方をするのがよいでしょう。
獣医師Q&A
熱中症になったらどんな治療をするの? 入院することもある?
熱中症になった場合には、その症状の進行度合いや内容によって処置が変わります。
基本的には体温を下げることと、失われている水分を点滴などで補給しながら経過を観察します。
症状が進んでいると内臓の働きにも影響が出てくることがあり、必要に応じて入院を要することもございます。
基本的には体温を下げることと、失われている水分を点滴などで補給しながら経過を観察します。
症状が進んでいると内臓の働きにも影響が出てくることがあり、必要に応じて入院を要することもございます。
暑くなったらサマーカットにすれば、暑さ対策は完璧?
ダブルコートである場合や、毛量の多い犬種については放熱しやすくなるため、予防効果は見られます。ただし、サマーカットだけでは不十分です。サマーカットはプラスアルファの対策として導入してみましょう。
個体差はありますが、極端なカットをおこうと毛質が変化する、被毛が生えにくくなるなどの可能性が出たり、日光や紫外線による皮膚への影響がみられたりすることもあるため、かかりつけの先生と相談しながら進めましょう。
個体差はありますが、極端なカットをおこうと毛質が変化する、被毛が生えにくくなるなどの可能性が出たり、日光や紫外線による皮膚への影響がみられたりすることもあるため、かかりつけの先生と相談しながら進めましょう。
扇風機をつけていればエアコンはいらない?
扇風機やサーキュレーターは空気を循環することで、熱がこもりにくい状況を作ったり汗の気化熱を利用し涼しくしたりするものです。そのため、汗をかけない犬にとっては冷涼効果は乏しいです。
しかし、扇風機をうまく併用することでエアコンの設定温度を少し上げることはできるため、うまく活用することで節電につながります。
また、扇風機を利用する際には犬に風が直接当たらないように気をつけましょう。
しかし、扇風機をうまく併用することでエアコンの設定温度を少し上げることはできるため、うまく活用することで節電につながります。
また、扇風機を利用する際には犬に風が直接当たらないように気をつけましょう。
獣医師からのメッセージ
熱中症は言葉を発することができず、温度調整が苦手な分、人よりも犬のほうが発症しやすくなります。
熱中症に対する意識は高くなっているものの、発症する犬は0ではありません。ひんやりグッズや対策はあくまでも補助としてとらえ、過信しないようにしましょう。
日没後でも犬の歩く高さでは高気温です。お散歩前に地面が熱くないか、犬の高さでの温度を確認してから出発するようにしてください。散歩の時間をうまく調整できないときにはひんやりグッズを用いながら短時間ですませ、おうちでたくさん遊んであげましょう。
熱中症になったとしても症状が進むまで気付くことが難しいこともあります。日頃の愛犬の様子をよく見ておき、わずかな異変でも気が付けるようにしておくことが大切です。
屋外はもちろんのこと、屋内でもリスクは同等なので、常に犬の体調にも意識して熱中症を予防していきましょう。
熱中症に対する意識は高くなっているものの、発症する犬は0ではありません。ひんやりグッズや対策はあくまでも補助としてとらえ、過信しないようにしましょう。
日没後でも犬の歩く高さでは高気温です。お散歩前に地面が熱くないか、犬の高さでの温度を確認してから出発するようにしてください。散歩の時間をうまく調整できないときにはひんやりグッズを用いながら短時間ですませ、おうちでたくさん遊んであげましょう。
熱中症になったとしても症状が進むまで気付くことが難しいこともあります。日頃の愛犬の様子をよく見ておき、わずかな異変でも気が付けるようにしておくことが大切です。
屋外はもちろんのこと、屋内でもリスクは同等なので、常に犬の体調にも意識して熱中症を予防していきましょう。
まとめ

熱中症を発症する原因から発症した場合の症状、応急処置までを解説しました。
また、体型や犬種特徴からとくに暑さに弱いといわれている犬種をご紹介しました。
どのタイプの犬を飼うことになっても、室内温度や散歩時間に気を配るなど徹底して対策をおこない、愛犬に快適で安全な生活を提供してあげましょう。
また、体型や犬種特徴からとくに暑さに弱いといわれている犬種をご紹介しました。
どのタイプの犬を飼うことになっても、室内温度や散歩時間に気を配るなど徹底して対策をおこない、愛犬に快適で安全な生活を提供してあげましょう。