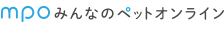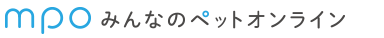狂犬病ワクチンの接種時期と費用

狂犬病ワクチンは、生後90日を過ぎてから打つことができます。生後何か月の子犬を迎えるかによって、接種タイミングが決まるので注意しましょう。
接種時期
生後90日以内の場合
お迎えした犬が生後90日以内であれば、飼いはじめてからの期間に関わらず、生後90日を経過した日から30日以内に接種をします。
はじめての接種は畜犬登録と同じタイミングになることが多い※ので、同時期におこなうと効率的でしょう。
※犬の所有者を明確にするために、畜犬登録する必要があります。犬を飼う人全員に対する義務であり、引っ越しや所有者を変更する場合は、その都度届け出が必要です。
関連する記事
はじめての接種は畜犬登録と同じタイミングになることが多い※ので、同時期におこなうと効率的でしょう。
※犬の所有者を明確にするために、畜犬登録する必要があります。犬を飼う人全員に対する義務であり、引っ越しや所有者を変更する場合は、その都度届け出が必要です。
生後90日を過ぎている場合
生後90日を過ぎてからお迎えした場合は、飼いはじめた日から30日以内に接種をします。
狂犬病ワクチンの接種が終わったら
狂犬病ワクチンの接種が終わり、接種したことの証明書(狂犬病予防注射済証)を動物病院でもらったら、それを近くの自治体の役所や保健所に持って行きましょう。手続きが完了すると狂犬病予防注射済票がもらえます。
畜犬登録は一生に1回ですが、狂犬病予防注射済票交付の手続きは毎年する必要があります。
狂犬病予防注射済票は、一部動物病院では、その場で登録~交付をしてくれるところもあるので、かかりつけ医もしくは近くの動物病院に確認しましょう。
2年目からは自治体から案内の手紙やハガキが届きます。毎年4~6月に集団接種がおこなわれており、接種を終えたら必ず証明書を提出してください。
自治体によって各対応が異なる場合がありますので、かかりつけ医や自治体に確認しましょう。
畜犬登録は一生に1回ですが、狂犬病予防注射済票交付の手続きは毎年する必要があります。
狂犬病予防注射済票は、一部動物病院では、その場で登録~交付をしてくれるところもあるので、かかりつけ医もしくは近くの動物病院に確認しましょう。
2年目からは自治体から案内の手紙やハガキが届きます。毎年4~6月に集団接種がおこなわれており、接種を終えたら必ず証明書を提出してください。
自治体によって各対応が異なる場合がありますので、かかりつけ医や自治体に確認しましょう。
ワクチン接種のスケジュールを立てよう
狂犬病ワクチンのほかに混合ワクチンというものがあります。
混合ワクチンは生後おおよそ半年までの間に3回、その後は1年に一度接種するというのが基本的なペースになります。
迎えた子犬に、混合ワクチンの接種も必要だと分かった際には、以下に気を付けましょう。
これまでに接種したワクチンと接種日を確認し、かかりつけ医と相談をしてワクチンスケジュールを立てましょう。
混合ワクチンは生後おおよそ半年までの間に3回、その後は1年に一度接種するというのが基本的なペースになります。
迎えた子犬に、混合ワクチンの接種も必要だと分かった際には、以下に気を付けましょう。
- 狂犬病ワクチンと混合ワクチンは同時に打てない
- <狂犬病ワクチン→混合ワクチンの場合>
狂犬病ワクチン接種日から、1週間あける - <混合ワクチン→狂犬病ワクチンの場合>
混合ワクチン接種日から1カ月あける(ただし不活化ワクチンのみの場合は1週間でよい)
これまでに接種したワクチンと接種日を確認し、かかりつけ医と相談をしてワクチンスケジュールを立てましょう。

ワクチン接種の頻度は獣医師に相談しよう
原田 友紀先生
混合ワクチンについて、国際ガイドラインから、コアワクチン(命にかかわる重篤な病気にかかわるワクチンで、抗体価の持ちがいいもの)に関しては、抗体価が十分あるのであれば、1年に1回打たなくてもいいとする病院も増えています(学術的には3年に一度で十分とも言われています)。
ただ、お住まいの地域の感染状況、生活環境等によっては、混合ワクチンに含まれているもののうち、抗体価が減るのが早い病気について、毎年接種することもあります。かかりつけの先生に確認していただくといいでしょう。
ただ、お住まいの地域の感染状況、生活環境等によっては、混合ワクチンに含まれているもののうち、抗体価が減るのが早い病気について、毎年接種することもあります。かかりつけの先生に確認していただくといいでしょう。
接種場所
狂犬病ワクチンを接種できる場所は、大きく分けて2カ所あります。
ひとつは動物病院、もう1カ所は保健所、公民館、動物愛護フェスティバル会場など、各自治体が主催する集団接種会場です。
それぞれのメリット・デメリットをみていきましょう。
ひとつは動物病院、もう1カ所は保健所、公民館、動物愛護フェスティバル会場など、各自治体が主催する集団接種会場です。
それぞれのメリット・デメリットをみていきましょう。
動物病院
<メリット>
<デメリット>
- かかりつけ医だと愛犬の病歴や性格などを把握してくれている
- 日程の調整ができる
- 接種ついでに各種健康診断や検診、健康相談をお願いできる(病院によっては当日受診内容の変更が難しいところもあるので、かかりつけに確認しましょう)
<デメリット>
- ワクチン代とは別に、診察料等が発生する
- 動物病院は自由診療なので、ワクチン代の価格差が出ることもある
- 注射済票の交付手続きがその場でできる病院と、できない病院がある(飼い主が狂犬病接種済み証明書を持参し、役所や保健所に手続きをしに行かなくてはならない場合がある)
集団接種
<メリット>
<デメリット>
関連する記事
- ワクチン代のみで、診察料等がかからない
- その場で狂犬病予防注射済票がもらえる
<デメリット>
- 日程と接種会場場所が限られている
- 集団接種なのでほかの犬を怖がる犬には向いていない
- 狂犬病の接種のみをおこなっているため、検診や相談などは難しい
費用
かかる費用は、
畜犬登録手数料は3,000円前後と各自治体で決められており、直接でも代行でも支払う場所によっての価格差はありません。登録料は初回のみなので、2回目からはかかりません。
ワクチン代はおよそ2,000~4,000円で、病院によって差があります。また、この金額のなかには狂犬病接種済票交付料(500円程度)が含まれている場合もあるので、病院に確認しましょう。
- 畜犬登録手数料(3,000円程度)
- ワクチン代(2,000~4,000円程度)
- 狂犬病接種済票交付料(500円程度)
畜犬登録手数料は3,000円前後と各自治体で決められており、直接でも代行でも支払う場所によっての価格差はありません。登録料は初回のみなので、2回目からはかかりません。
ワクチン代はおよそ2,000~4,000円で、病院によって差があります。また、この金額のなかには狂犬病接種済票交付料(500円程度)が含まれている場合もあるので、病院に確認しましょう。

病院や地域などによって費用は異なる
原田 友紀先生
病院だけでなく、都道府県によっても若干価格が異なることがあるので、集団接種でも地域によって若干料金が変わる可能性もあります。お住まいの自治体のそれぞれの手数料がいくらなのか確認してみましょう。
狂犬病とは

狂犬病とは、狂犬病ウイルスによって引き起こされる感染症です。
人を含むすべての哺乳類が感染します。
感染してから発症するまでの潜伏期間が非常に長いのが特徴で、一般的には1~3カ月、長いものでは感染してから1~2年後に発症した事例もあります。
また、発症するとほぼ100%死亡するといわれている、有効な治療法のない人獣共通感染症(ズーノーシス)です。
人を含むすべての哺乳類が感染します。
感染してから発症するまでの潜伏期間が非常に長いのが特徴で、一般的には1~3カ月、長いものでは感染してから1~2年後に発症した事例もあります。
また、発症するとほぼ100%死亡するといわれている、有効な治療法のない人獣共通感染症(ズーノーシス)です。
媒介動物と感染経路
媒介動物
犬、猫、コウモリ、アライグマ、キツネなどが多く報告されています。
感染経路
感染動物の唾液が感染源で、咬まれる、唾液が付着した爪で引っかかれる、傷口や目や口の粘膜を舐められることで感染。
通常、人から人に感染することはなく、感染した患者から感染が拡大することはないといわれています。
犬、猫、コウモリ、アライグマ、キツネなどが多く報告されています。
感染経路
感染動物の唾液が感染源で、咬まれる、唾液が付着した爪で引っかかれる、傷口や目や口の粘膜を舐められることで感染。
通常、人から人に感染することはなく、感染した患者から感染が拡大することはないといわれています。
狂犬病の潜伏期間と症状
犬の場合
潜伏期間は2週間~2カ月程度、症状は下記のように進んでいきます。
病気の進行は早く、多くの場合1週間ほどで死に至ります。
- 前駆期
性格の変化と行動の異常 - 狂躁期
興奮、無目的な徘徊、光や音に対する過敏な反応など - 麻痺期
全身の麻痺症状による歩行不能、下顎の下垂、えん下困難など。昏睡状態になり死亡
病気の進行は早く、多くの場合1週間ほどで死に至ります。
人間の場合
潜伏期間は犬より長く、1~3カ月ほどで、症状は下記のように進行します。
この恐ろしい病気の感染を防ぐために、国内にすむ飼い犬には狂犬病の予防接種が義務付けられているのです。
- 前駆期
発熱、食欲不振、口傷部位の痛みなど - 急性神経症状期
不安感、恐水および恐風症状、興奮、麻痺、幻覚、精神錯乱などの神経症状 - 昏睡期
昏睡(呼吸障害)によりほぼ100%死亡
この恐ろしい病気の感染を防ぐために、国内にすむ飼い犬には狂犬病の予防接種が義務付けられているのです。
参考文献
狂犬病ワクチンの重要性と義務

ワクチン接種の重要性
狂犬病は有効な治療法のない感染症で、発症した場合にはほぼ100%死亡します。
すべての哺乳類に感染しますが、蔓延の原因となる動物は限られていて、アジアなど狂犬病流行国では犬が主な蔓延源となっています。
したがって、犬に予防接種することで蔓延を防止し、人への感染も防ぐことができます。
すべての哺乳類に感染しますが、蔓延の原因となる動物は限られていて、アジアなど狂犬病流行国では犬が主な蔓延源となっています。
したがって、犬に予防接種することで蔓延を防止し、人への感染も防ぐことができます。
狂犬病ワクチン接種義務
1950年に狂犬病予防法が施行され、行政は積極的に野良犬を捕獲し、蔓延予防に努めることとし、犬の所有者には飼い犬に対しての狂犬病ワクチン接種が義務化されました。
それにより1957年以降、国内発生はみられなくなりました。しかし、最近でも2020年に1件、輸入感染症例が確認されており、海外では現在でも多くの感染者が報告されています。
万が一、狂犬病が国内に侵入した場合に備え、飼い犬への毎年のワクチン接種を徹底しましょう。
それにより1957年以降、国内発生はみられなくなりました。しかし、最近でも2020年に1件、輸入感染症例が確認されており、海外では現在でも多くの感染者が報告されています。
万が一、狂犬病が国内に侵入した場合に備え、飼い犬への毎年のワクチン接種を徹底しましょう。
注射済票と鑑札の交付・装着
畜犬登録をおこない、狂犬病ワクチンを接種すると、鑑札※と狂犬病予防注射済票が交付されます。これは「犬の所有者・所在地」と「狂犬病ワクチンを接種した犬である」ことを示す標識で、装着を義務付けられています。
印字された番号と飼い主情報は紐づけされており、ハーネスや首輪に装着できる素材と形状になっています。
トリミングサロンやペットホテル、ドッグランなどの施設を利用の際には、掲示を求められることがほとんどです。普段からつけておくことをおすすめします。
年度がかわり、接種しなおすと、新しいものを交付されます。付け替えも忘れないようにしましょう。
※マイクロチップを装着していることで、鑑札が交付されない場合もあります(自治体によって対応が異なります)
印字された番号と飼い主情報は紐づけされており、ハーネスや首輪に装着できる素材と形状になっています。
トリミングサロンやペットホテル、ドッグランなどの施設を利用の際には、掲示を求められることがほとんどです。普段からつけておくことをおすすめします。
年度がかわり、接種しなおすと、新しいものを交付されます。付け替えも忘れないようにしましょう。
※マイクロチップを装着していることで、鑑札が交付されない場合もあります(自治体によって対応が異なります)
狂犬病ワクチンが猶予されるケース
病気や妊娠、狂犬病ワクチンによるアナフィラキシーショックなどが理由で、ワクチン接種が犬の健康や命に影響を及ぼすかもしれないと獣医師が判断した場合、「狂犬病予防接種実施猶予証明書」が発行されます。
正確には「免除」ではなく、この年の実施を次の年まで「猶予」するというものです。
来年もということであれば、再度獣医師の判断と証明書が必要になります。
法律で狂犬病ワクチン接種は義務付けられていますが、体調面で不安なことがある場合は必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。
正確には「免除」ではなく、この年の実施を次の年まで「猶予」するというものです。
来年もということであれば、再度獣医師の判断と証明書が必要になります。
法律で狂犬病ワクチン接種は義務付けられていますが、体調面で不安なことがある場合は必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。

自己判断せず、獣医師や自治体に相談を
原田 友紀先生
何らかの病気の治療中であったり、持病がある、など、狂犬病ワクチンを打つことで、病気からの回復や健康を阻害する可能性があると獣医師が判断した場合は「狂犬病予防注射猶予証」を出してもらえることがあります。
ほかに、過去に狂犬病ワクチンを打ったことでアナフィラキシー症状をおこしたことがある子や、妊娠中のわんちゃんなども猶予証明書を発行してもらえることも。猶予証明書をもらったあとは、お住まいの自治体の決まりに従って自治体に証明書の提出をしましょう。
また、自治体によって、基準や手続きが異なることがあります。必ず、かかりつけの先生や自治体に確認が必要です。
ほかに、過去に狂犬病ワクチンを打ったことでアナフィラキシー症状をおこしたことがある子や、妊娠中のわんちゃんなども猶予証明書を発行してもらえることも。猶予証明書をもらったあとは、お住まいの自治体の決まりに従って自治体に証明書の提出をしましょう。
また、自治体によって、基準や手続きが異なることがあります。必ず、かかりつけの先生や自治体に確認が必要です。
狂犬病ワクチンの注意点

接種前
接種日を決める
接種日時を選べる場合は、かかりつけの病院の午後が休診になっていない日の午前中を選択しましょう。
万が一、ワクチン後アレルギーの症状があらわれたときにすぐに病院に相談できるようにするためです。集団接種の場合も、もしものことを考えて、かかりつけ動物病院が開いている時間を選択すると安心でしょう。
また、以下の場合は事前にかかりつけ医に相談し、接種をしてもよいか、指示を仰いでください。
万が一、ワクチン後アレルギーの症状があらわれたときにすぐに病院に相談できるようにするためです。集団接種の場合も、もしものことを考えて、かかりつけ動物病院が開いている時間を選択すると安心でしょう。
また、以下の場合は事前にかかりつけ医に相談し、接種をしてもよいか、指示を仰いでください。
- 病気で通院中
- 薬を服用中
- 持病がある
- 妊娠中
- 出産直後
- 1年以内にてんかん発作を起こしたことがある
- 高齢で体力や体調に不安がある
- 過去にワクチンでアナフィラキシーショックを起こしたことがある
接種日当日
当日、愛犬の体調に不安がある場合は延期をしたほうがよいでしょう。判断に困る場合は、かかりつけに相談するなどしましょう。
また、狂犬病ワクチンを接種する日と同じ日に、ほかのワクチン接種や、ノミ・ダニ駆除薬、フィラリア駆除薬の投与はできません。
また、狂犬病ワクチンを接種する日と同じ日に、ほかのワクチン接種や、ノミ・ダニ駆除薬、フィラリア駆除薬の投与はできません。
接種後
アナフィラキシー症状(虚脱、血圧低下、呼吸困難、けいれん、尿失禁など)が出る可能性があるため、接種後15~30分は特によく様子を観察し、異変を感じたらすぐに受診をしてください。
激しい運動は2~3日程度、シャンプーは1週間ほど控えましょう。
激しい運動は2~3日程度、シャンプーは1週間ほど控えましょう。
副反応の可能性
狂犬病ワクチンの安全性は非常に高いといわれていますが、ほかのワクチン同様、リスクは残念ながらゼロではありません。
接種は必ず体調がよいときにうけ、接種後しばらくは愛犬の様子をしっかり観察しましょう。
副反応の症状はいろいろありますが
など、普段と違う様子がみられたら病院に連絡をし、相談してください。
関連する記事
接種は必ず体調がよいときにうけ、接種後しばらくは愛犬の様子をしっかり観察しましょう。
副反応の症状はいろいろありますが
- 元気消失
- 食欲不振
- 嘔吐や下痢
- 蕁麻疹など皮膚トラブル
- 呼吸困難や過呼吸などの呼吸器系トラブル
- 震え
- 接種部位の一時的な腫れや疼痛(とうつう)
- 発熱
- ムーンフェイス(顔の腫れや痒み)
など、普段と違う様子がみられたら病院に連絡をし、相談してください。
獣医師からのメッセージ
日本では1957年から狂犬病は発生していないため、過去の病気として忘れ去られ、予防意識の低下がみられます。
令和元年の登録犬の狂犬病予防接種率は71.3%ですが、登録されていない犬も含めると日本全体では50%以下と言われ、今のままでは万が一狂犬病が国内に入ってきてしまった場合、狂犬病の蔓延を防ぐことはできず、未接種の子に対してかなり厳しい対応がとられることも予想されます。
狂犬病は発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。日本の周辺国を含む海外では年間6万人近くの人が亡くなっています。人や動物の移動が活発になっている昨今、いつ日本に再び狂犬病が侵入してくるかわかりません。
狂犬病の蔓延を防ぐため、愛犬の命をまもるためにも、わんちゃんの予防を徹底し、わんちゃんの命だけでなく自分を含めた人々の命を守っていきましょう。
令和元年の登録犬の狂犬病予防接種率は71.3%ですが、登録されていない犬も含めると日本全体では50%以下と言われ、今のままでは万が一狂犬病が国内に入ってきてしまった場合、狂犬病の蔓延を防ぐことはできず、未接種の子に対してかなり厳しい対応がとられることも予想されます。
狂犬病は発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です。日本の周辺国を含む海外では年間6万人近くの人が亡くなっています。人や動物の移動が活発になっている昨今、いつ日本に再び狂犬病が侵入してくるかわかりません。
狂犬病の蔓延を防ぐため、愛犬の命をまもるためにも、わんちゃんの予防を徹底し、わんちゃんの命だけでなく自分を含めた人々の命を守っていきましょう。
まとめ

愛犬に狂犬病ワクチンを接種することは、義務であり、誰も悲しい思いをしないで済むよう飼い主としての責任であり、もっとも有効な予防法です。
万が一、誰かを噛んでしまった場合にも、ワクチンを接種していれば最悪の事態は免れます。
愛犬が誰かに噛みつくなんて考えられないとしても、よその犬から噛まれる可能性は否定できません。
犬と人間のどちらも、安心して過ごすために、年に一度のワクチン接種をしっかりと受けましょう。
狂犬病の接種の時期やタイミング、手続きのやり方等は自治体によって異なることがあります。お住まいの地域のかかりつけの先生や、自治体の担当部署などへの確認をお願いいたします。
関連する記事
万が一、誰かを噛んでしまった場合にも、ワクチンを接種していれば最悪の事態は免れます。
愛犬が誰かに噛みつくなんて考えられないとしても、よその犬から噛まれる可能性は否定できません。
犬と人間のどちらも、安心して過ごすために、年に一度のワクチン接種をしっかりと受けましょう。
狂犬病の接種の時期やタイミング、手続きのやり方等は自治体によって異なることがあります。お住まいの地域のかかりつけの先生や、自治体の担当部署などへの確認をお願いいたします。